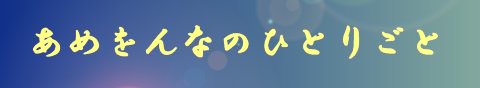


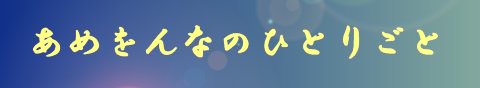 |
 |
 |
 | 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008



 | 2009
| 2009



 | 2010
| 2010
 | etc
| etc



|
二〇〇八年夏の俳句(一)
草の間にぬれて青梅転がれり*
|
|
二〇〇八年夏の俳句(二)
芍薬にかがめば首のあつくなり
|
|
二〇〇八年夏の俳句(三)
初音町寺の合ひ間の枇杷青し
|
|
二〇〇八年夏の俳句(四)
でで虫の子の細き葉に連なれり
|
|
二〇〇八年夏の俳句(五)
三伏の水に求むる水の音
|
|
二〇〇八年夏の俳句(六)
でで虫を拾へば軽き夏の道+
|
|
二〇〇八年夏の俳句(七)
風向きのヨットに見ゆる岬かな
|