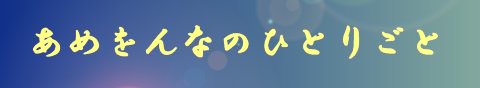


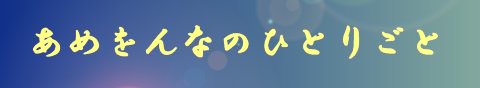 |
 |
 |
 | 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008



 | 2009
| 2009



 | 2010
| 2010
 | etc
| etc



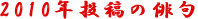
|
二〇一〇年投稿の俳句(一)
口中に梅干ふふみ雪見酒
|
|
二〇一〇年投稿の俳句(二)
菜の花の根本あかるき土の色
|
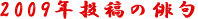
|
二〇〇九年投稿の俳句(一)
田の隅に松立ててあり初仕事
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(二)
木の名札木の間に鳴れり春寒し
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(三)
じやが植うる空どこまでも晴れてをり
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(四)
浅からず深からぬ濠夏つばめ
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(五)
暗闇に鍵穴探す虫しぐれ
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(六)
紅葉且つ散る子の声は明るくて
|
|
二〇〇九年投稿の俳句(七)
寒林のこまかに羽根をつかふ鳥
|
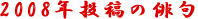
|
二〇〇八年投稿の俳句(一)
初午や舌が真つ赤になりし飴
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(二)
草青むテニスコートの四隅より
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(三)
花衣日向日陰を出入りかな
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(四)
春月夜筑波嶺低き山であり*
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(五)
緋目高の卵をはなす震へかな
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(六)
梅漬をひと揺すりする雨間かな*
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(七)
かはほりの子のももいろに脈打てり*
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(八)
粉殻の山輝かす夕日かな
|
|
二〇〇八年投稿の俳句(九)
朴落葉みな裏返り土の上
|
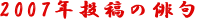
|
二〇〇七年投稿の俳句(一)
うばぐるま押す幼子や春の泥
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(二)
山茱萸の花白壁の内にあり*
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(三)
ふらここや手のひら鉄気くさくなり
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(四)
藤の雨フォロ・ロマーノへ浸みとほり
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(五)
大海へ波間波間の海月かな*
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(六)
待たせるといふこともあり合歓の花
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(七)
露しづくこぼして蓮の花咲けり
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(八)
朝顔やネヂ一本を町工場
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(九)
それぞれの花を手向けて秋の昼
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(十)
空もまた色なかりけり枯野中
|
|
二〇〇七年投稿の俳句(十一)
冬の菊訥訥とある竿師かな
|